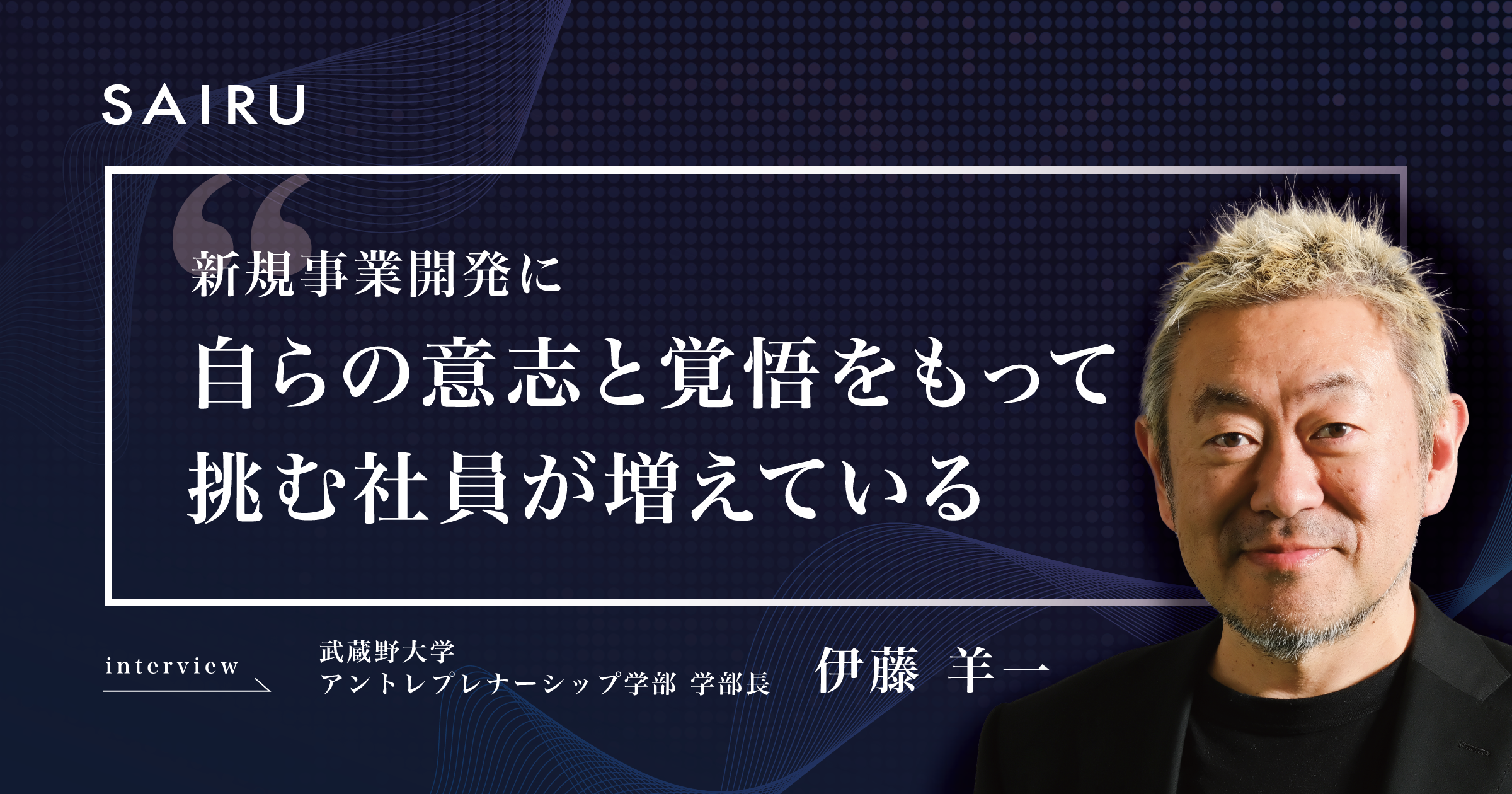
大手企業で新規事業開発を支援する組織・個人に焦点を当てる連載「新規事業開発を支援する人たち」。
今回は特別編として、武蔵野大学 アントレプレナーシップ学部・学部長の伊藤羊一さんに、お話を伺いました。
長年、大手企業の新規事業開発に携わってきた伊藤さん。近年の変化として、「大手企業における新規事業開発の姿勢には、明らかな変化を感じている」と力強く語ります。その背景には、「自らの意志と覚悟を持って挑む社員が増えている」というのです。
では、企業はこの潮流にどう対応すべきか? 伊藤流「新規事業開発のアプローチ」と、武蔵野EMCの学部長として学生たちと日々向き合うなかから見出した「アントレプレナーシップ醸成の黄金律」をお届けします。

Musashino Valley 代表
アントレプレナーシップを抱き、世界をより良いものにするために活動する次世代リーダーを育成するスペシャリスト。2021年に武蔵野大学アントレプレナーシップ学部(武蔵野EMC)を開設し学部長に就任。2023年6月にスタートアップスタジオ「Musashino Valley」をオープン。「次のステップ」に踏み出そうとするすべての人を支援する。また、株式会社ウェイウェイ代表として次世代リーダー開発を行う。代表作『1分で話せ』(SBクリエイティブ)は67万部超のベストセラーに。
大手企業の新規事業開発は「任務」から「使命」へ
ーー伊藤さんは新規事業開発に関する相談を受ける機会が多いと思います。大手企業の新規事業開発の傾向に変化を感じられますか?
伊藤 私はこれまで十数年にわたり、大手企業の新規事業開発に関わってきました。プラス株式会社やヤフー株式会社(当時)在籍時は自ら事業を立ち上げたほか、大手企業がスタートアップとの共創を目指すアクセラレータープログラムのメンターを経験。現在は経済産業省が主催する「始動 Next Innovator(グローバル起業家等育成プログラム)」の講師もしています。
そのようななか、大手企業における新規事業開発の姿勢には、明らかな変化を感じています。何より、市場縮小や競争の激化によって、企業側も本気で事業開発に取り組まざるを得ない状況にありますよね。
そして、以前は会社の命令で仕方なく取り組むケースが多かったものですが、最近では自らの意志と覚悟をもって挑む社員が増えている。仮に実現が難しければ、会社を辞めてでも起業するという気概と熱意をもつ人も現れています。
この変化の背景には、いくつかの社会的要因があります。まず、クラウドサービスの登場により、サービス開発や法人設立などのコストが劇的に下がり、起業の物理的ハードルが低くなったこと。さらに周囲で起業する人が増え、「自分にもできるかもしれない」と起業への心理的なハードルが下がってきていることです。
加えて、社会全体のニーズや課題が細分化・多様化し、「この問題を自分が解決したい」という想いを持つ人が増えています。大きな自然災害やコロナ禍によって日本の秩序や常識が崩れていくなかで、「自分の人生はこのままでいいんだろうか?」「新しいことをやらなくちゃだめだ」という世の中になっていると感じますね。
大手企業が直面する壁。新規事業と既存事業の対立構造、体験創出への転換
ーー大手企業の新規事業開発にポジティブな変化が見られる一方で、依然として変わらない課題はありますか?
伊藤 企業は大きくなればなるほど、既存事業の維持と発展が中心となり、そこに携わる社員が多数を占めるようになります。結果として、売上の目処が不透明な新規事業を軽視する空気が生まれがちです。
新規事業は、既存の体制やサービスを前提としないため、既存事業と対立構造になりやすい。とくに人事評価においては、売上を大きく創出している既存事業と、結果が出るまでに時間がかかる新規事業を同じモノサシで測ることは、公平性を欠くだけでなく、イノベーションの芽も潰しかねません。
こうした構造的な矛盾を乗り越えるには、経営層が新しい挑戦の重要性を社内に強く打ち出す必要があります。しかし、現実にはそのような発信が不十分な企業も多いですね。
また、ユーザーニーズの変化により、モノではなく体験が求められている。これらの状況に対応するには、新規事業はもちろん、既存事業に関わる人々の意識改革も不可欠です。過去の成功体験やアセットに固執することなくユーザーニーズの本質を理解し、柔軟に考え、取り組む姿勢が求められます。
新規事業は「出島」で取り組み、夢を語れる風土で育てる
ーー既存事業と新規事業の対立構造や、顧客ニーズの変化に対応したプロダクト・サービス開発への対応。こうした課題解決には、何ができるでしょうか。
伊藤 大きく2つあります。1つ目は、出島戦略による物理的・制度的な分離です。出島戦略とは、新規事業のチームを既存事業と切り離し、評価基準や報酬制度をはじめ、働くオフィスや服装もすべてを別のものとして設計すること。虎ノ門ヒルズにあるARCH(※)のように、業種を超えた新規事業担当者が集まって自由に交流できる環境を用意するのも手です。
2つ目は、夢を語りあう文化を醸成すること。「うちはものづくりの会社だから」という前提でプロダクトの改善を目指すのではなく、「人類がよりハッピーになるには?」と、根源的な問いから理想の生活像を描き、そこからプロダクトやサービスを逆算する発想が必要です。
日本には、現実離れした理想や夢を語ることを良しとしない空気感がありますよね。私が学部長を務めている武蔵野大学のアントレプレナーシップ学部(武蔵野EMC)では、人の夢を笑わない空気を大切にしています。
「イーロン・マスクを超える」といった突拍子もない夢であっても、否定する人はいません。「最高だね!どうやる?」と本気で向き合うんです。こうした姿勢は、既存の価値観に囚われずに新しい挑戦を後押しする土壌になります。
会社においても同じです。妄想や空想も、立派な仕事であるとする空気づくりが、新しい価値を生み出す一歩になるのではないでしょうか。
※ARCH(アーチ):虎ノ門ヒルズ ビジネスタワーに拠点を置く、大企業の事業改革や新規事業創出に特化したインキュベーションセンター。森ビル株式会社が運営。
既存事業のアセットは、活かしてこそ価値になる
ーー大手企業の新規事業開発には、当然ながら多くの利点もあると思います。具体的にどんな利点があるのか、また利点を活かすために必要なポイントは何でしょうか?
伊藤 利点として真っ先に挙がるのが、これまで築き上げてきた技術力や生産能力、人的リソースなど豊富なアセットです。たとえば特許技術がある場合は、他の企業では再現できない強みとなります。
また、販売チャネルやネットワークも長年の事業活動による賜物で、大手企業ならではの優位性といえます。これらの資源を最大限に活用できれば、新規事業が成功する可能性は高まります。
しかし問題は、こうしたアセットが実際に使えるかどうか。既存事業側からの反発によって活用できないケースが多く存在するからです。つまりアセットがあるだけでは不十分で、使えるようにマネジメント側が交通整理をすることが必要不可欠です。
かつて大手企業の新規事業開発は、既存事業とのシナジーを重視する方針が一般的でした。結果として既存事業との連携を求められ、柔軟な動きが制限されることが多々ありました。こうした背景を踏まえると、シナジーに頼らず新しいことを自由に始めるか、もしくはシナジーを求めるなら既存事業のアセットを最大限活用する体制を整える必要があります。
アントレプレナーシップは対話で醸成する
ーー新規事業開発では、新しいことにチャレンジする人材の育成やアントレプレナーシップの醸成も欠かせません。人材育成の観点で支援者のあるべき心構えについても聞かせてください。
伊藤 アントレプレナーシップの本質は、自分の思いに従って新しい価値を生むことだと思います。会社にやれと言われたからやる、というのは単なる作業ですよね。そもそもアントレプレナーシップは起業家や新規事業の担当者に限らず、誰もが持っているべきものなんです。
人材育成や支援者側の心構えとして大切なのは、「こうしろ」と一方的に指示するのではなく、個人個人が自らの意思で道を選び、価値を生み出していけるよう後押しをする姿勢です。
では具体的にどうしたらいいのか。武蔵野EMCではこの3月に1期生が卒業しました。卒業生を間近で見ていて、間違いないと確信に至ったアントレプレナーシップ醸成の黄金律があります。
それは、「刺激を受け、自分で考え、みんなで話し、気づきを得て、やってみる」というサイクルです。
このサイクルを何度も回すことで、アントレプレナーシップは自然と醸成されます。とくに肝となるのは対話で、意図的に会話の総量を増やす環境づくりが大切です。
武蔵野EMCの1年生は、全員が寮生活を送ります。朝も夜も、日常的に話し合う文化の醸成が目的です。親からの影響を適度に切り離した環境で、内省と対話を通じた気づきを得ることにより、内発的な動機が引き出されます。

アントレプレナーシップ醸成の黄金律
刺激的を受ける(Input)
好奇心を掻き立てるような刺激を受けることで、探究心が刺激され、学びや行動へのモチベーションが生まれます。自分で考える
受けた刺激について、自ら考えます。みんなで話してみる
自分で考えた後は、みんなで話をします。話すことで自分のなかのモヤモヤが言語化されて気付きが生まれ、シナプスが刺激されます。Aha!
対話から、「Aha!こういうことか!」と気づきが生まれます。やってみる(Output)
気づいたことや、思いついたことを行動に移します。
伊藤 日本人や日本のビジネスパーソンは、比較的、黙って働く傾向がありますよね。それは、意図的に変えられます。たとえば本田技研工業には、夢や仕事のあるべき姿などについて、世代や職位にとらわれず、ワイワイガヤガヤと議論する「ワイガヤ」という文化があります。みなさんも、対話の機会を意識的に設けてみてはいかがでしょうか。
ーーリモートワークの広まりによって、対話の機会が減っているのでしょうか。
伊藤 必ずしも、リアルなコミュニケーションが絶対というわけではありません。Slackのようなチャットツールを駆使して、意識的にコミュニケーションの総量を増やせばいいのです。
それも事務的なやりとりだけでなく、無駄と思える会話も含めて、ざっくばらんに意見交換をする。ただし、雑談はオンラインではやりにくいので、週に一度でもリアルで集まって意見交換をする時間は大切です。
つまり「オンラインで量を確保し、リアルで質を高める」というハイブリッド型のコミュニケーションを取ればいい。
コミュニケーションの総量さえ増やせば、アントレプレナーシップは自然と醸成されるもの。なぜなら、アントレプレナーシップの源泉である「自分の想い」は対話を重ねるなかで明確になっていくからです。
日本を「失われた40年」にはしたくない。革命家の気持ちで、一歩を踏み出そう
ーー最後に、新規事業開発に関わる人たちへ、メッセージをお願いします。
伊藤 今の日本は「失われた30年」と呼ばれる停滞期を抜け出せず、このままでは「失われた40年」に突入する可能性すらある状況です。自分たちの会社がこのままで大丈夫か自問したとき、「絶対に大丈夫」と胸を張って言える企業は、ほとんどないのではないでしょうか。
現実は確かに厳しい。でも、不平不満を言っている場合ではありません。あなたの本気が、会社を、そして社会を変える力になります。あなたが一歩踏み出すことで、周囲も動き出します。「自分が革命を起こすんだ」という強い気持ちをもって取り組んでいきましょう。
(取材・執筆 藤井恵、編集 水谷真智子)
連載企画「新規事業開発を支援する人たち」
第1回 東京海上ホールディングス株式会社
応募者が増え続ける東京海上HDの事業創出プログラム「TIP」。事務局の親身な支援体制を聞く
第2回 株式会社日立製作所

