
ビジネス環境がめまぐるしく変わる現在、事業会社と支援会社の間に定着してきた「客と業者」の関係のままでは、新しい事業アイディアや前例のない課題の解決方法は生まれません。
事業会社と支援企業が対等な関係を築き、ともにビジネス課題を解決するための考え方や行動を探る連載『正解のない時代を拓く、新しい企業パートナーシップ』をお届けします。
第1回は、オリックス生命保険株式会社で執行役員を務め、IT部門を管掌されている児玉 英一郎さんを取材しました。
児玉さんは、日本アイ・ビー・エムやセールスフォース・ジャパンなどの支援企業の立場から、事業会社と関わってきました。事業会社へ転身後は、管掌するIT本部にIT専門職制度を導入しました。さらに、伝統的な保険業界でシステム開発の内製化を進めるなか、開発会社をはじめとした多くの支援企業と協力体制を築いています。
労働集約型のモデルで成長してきたIT業界。しかし、企業のIT戦略の複雑化やエンジニア不足といった問題により、事業会社のIT部門と開発会社の間には、新しいパートナーシップが求められています。
事業会社として、開発会社をはじめとした支援企業と本音で向き合い、その企業の力を引き出せるような存在になりたいと話す児玉さん。その思考の原点は、自身が支援企業時代に出会ったお客さまから学んだといいます。
児玉さんが考える企業パートナーシップと、事業会社に求められる姿勢についてうかがいました。
聞き手は、才流コンサルタントの高橋 歩です。

執行役員 IT本部管掌
1999年大学院修了後、ITベンチャー、独立系SIerを経て2006年から日本アイ・ビー・エムに移り7年間、ITプロセスコンサルタントとして活動。
2013年からセールスフォース・ジャパンにて、最重要顧客向けのアドバイザリー/プログラムマネジメント業務に従事。
2015年にオリックス⽣命保険株式会社に⼊社し、IT戦略プロジェクト推進部長、2017年10月にIT本部長に就任。2019年7月より現職。
1991年にオリックス・オマハ生命保険株式会社として設立。個人向け保険商品を中心に成長し、現在は法人・個人向けにバランス良く商品を展開。2021年に設立30周年を迎え、個人保険の保有契約件数は480万件にのぼる。
児玉さんが管掌するIT本部は、4つの部門で構成され、生命保険事業から自社業務システムまでシステム全般の開発・運用・保守を担う。2020年よりIT専門職制度を導入し、専門性の高いIT人材の採用や育成に力を入れている。
役員が社内外に言葉を発信し、リーダーシップを発揮する
高橋 児玉さんは、日本アイ・ビー・エム、セールスフォース・ジャパンなどの支援企業を経て、2015年にオリックス生命保険へ入社されました。現在IT本部管掌の執行役員として、SIerやシステム開発会社といったパートナー企業とは、どのような関わり方をしていらっしゃいますか。
児玉 私がIT本部長に就任した2017年から、年度末にお付き合いのあるパートナー企業の皆さまをお招きして、翌期の基本方針や計画のご説明に加え、施策に尽力いただいたパートナーを表彰するミーティングを開催しています。

児玉 私が支援企業時代に担当した一流たる企業は、自社ITの発展に貢献してくれたパートナー企業を取り上げ、公に評価する機会を必ず設けていました。また、競合関係にあるパートナー企業同士が切磋琢磨できるよう、自社の想いを伝える場を意識的につくられていました。
そのような取り組みを見てきましたから、事業会社である当社へ入社したときに、私どもが何を考え、重視しているかを、パートナーの皆さまへ直接お伝えする場をつくろうと考えたのです。
高橋 ミーティングは、期初ではなく年度末に行うんですね。
児玉 そうですね。新しい期がスタートするとさまざまな施策の検討に着手しますから、少しでも早めにお知らせすることを大切にしています。
パートナー企業には、何十年もお世話になっている会社もあれば、近年ご縁があり、取引が始まった会社もあります。当社のビジネスの現況や、IT組織として目指す方向性をお伝えし、その想いに共感を示してくださるパートナー企業が少しでも増やせたらと。
同時に、双方で健全な危機感を醸成したいと考えています。開発者やエンジニアの単価上昇や人員不足が問題視されるなか、労働集約型のビジネスモデルや開発スタイルのままでは、お互いが疲弊し、破綻してしまう。共通の問題意識を持ち、取り組み方を「変革」する必要性をご理解いただく場にもしているのです。
開催後に集計したアンケートでは、当社の方針や想いを直接聞くことができて参考になったといった高評価をいただいていますし、表彰を糧に頑張ってくださっているパートナー企業も多数いらっしゃいます。このような取り組みは、今後も拡大していきたいですね。

高橋 年に一回、児玉さんから感謝を伝え、これからの方針を発信する場がある。お互いの顔が見える場があることは素晴らしいですね。
児玉 感謝や方針を伝えるのは、当然のことながらパートナー企業だけでなく社内に対してもですね。自身が管掌するIT本部内でも、四半期に一度はAll Hands Meeting という名称の全体会議を開催しています。
これは私のコンサルタント時代の習慣から始めたものです。責任者である私自身が、日々変化する状況や方針をその意図や背景も含めて社員らに働きかけ、組織に共通の認識を持たせて、向かうべき方向を示すことは、当然の務めですので。
当社は経営と社員との間の距離が近い組織です。組織風土醸成のためには、役員の率先垂範(そっせんすいはん)が重要であり、役員自身が自ら取るべき行動をリーダーシップ宣言として社内にも公表しています。
高橋 今後の方針に対しては、すべてのパートナー企業から提案を受け付けているのでしょうか。
児玉 おっしゃるとおりです。私どもの想いに共感し、そして自社の強みをいかしてもらえる提案でしたら、いつでもうかがいます。ここ数年の間にも、当社でのビジネスを急激に拡大したパートナー企業は複数いらっしゃいます。
そのような変化が、保険という非常に安定したビジネスにおいても起きている。ですから、当社のITによるビジネス価値実現のために、パートナー企業にはビジネスチャンスと捉えていただけるとありがたいです。門戸は開いています。「当社と取引がある企業が有利になるか?」といったことも、一切ありません。
これまでの習慣にとらわれない関係が非連続な成長につながる
高橋 児玉さんは、システムの内製化を進めていらっしゃるとうかがいました。事業会社側のシステム内製化が進むと、これまで多くのエンジニアを派遣していたパートナー企業にとっては、厳しい局面に立たされているのではないでしょうか。
児玉 昨年、情報サービス企業の業界団体で講演した際にも同様のご質問をいただきました。金融機関は他の業界に比べてもシステムの数が多く、開発規模も大きいです。本質的な解決策であるかという議論は別として、全体的なトレンドとしての内製化を促進する動きも否定はしません。ただそれは、パートナー企業にとって、決して委託先との取引が減ったり、終わったりしてしまうという意味ではないのです。
現実として、当社であれば約480万件のお客さまの人生に寄り添う、社会的責務が大きい生命保険事業は、多くのパートナー企業の協力があってこそ成立しています。

児玉 しかし、これから労働人口が減る反面、ビジネス環境の急速な変化に伴ってサービスデリバリーのスピードも高めていかなくてはならない。ですからパートナー企業には、従来のいわゆる「人月商売」のビジネスモデルではなく、高度な専門性を持った方々のノウハウを提供する形態に転換していただきたい。
スキルが極めて高い人材やチームであれば、常駐・専任のアサインにはこだわりません。パートナー企業が組織として持つ能力を、長期的な目線で提供していただきたいのです。
一方、事業会社のIT部門もパートナー任せの状態から、変わっていかなければなりません。自分たちで技術を学び、パートナー企業と対等に話せるITのプロフェッショナルとして、自社のIT領域をリードする人材が求められます。
クラウドサービスの普及や浸透により、IT、デジタル領域における情報の非対称性が事業会社と支援企業との間でなくなりつつあります。たとえば、クラウドサービスの新機能のローンチを知るタイミングは、パートナー企業の社員と私たちとで差がありません。
私はよく「よーいドンだ」と言っています。
高橋 「よーいドン」ですか。スタートするタイミングが一緒、ということですね。
児玉 かつては、パートナー企業が事業会社へ最新の知見やベストプラクティスを提供するという関係がありました。しかし、特定の技術領域においては、事業会社のほうが知っているケースも増えているのです。
たとえば、生成AI。昨年の秋、当社にも大変多くのスタートアップやコンサル企業からご提案をいただきました。お話をうかがってみて「本当に生成AIを理解し、活用できているのだろうか?」と感じました。なぜなら、その頃には当社内で生成AIの検証と、私たちなりの試行錯誤を経て、全社内に展開を終え、活用段階に入っていたからです。
このように、ITやデジタルに関する知見であったとしても事業会社のほうがパートナー企業よりも明るい場合があるし、逆にパートナー企業のほうが、私ども以上に生命保険事業を理解している可能性もあり得る。
ですから、これまでの習慣に囚われないことが、今後非連続な成長を支援企業、事業会社双方が実現するうえで大切であると思います。

高橋 知見や情報を、教える・教わるという関係からの脱却が始まっている。一方で、年度末のミーティングなどで自社の方針や戦略をオープンにすることに、不安はないのでしょうか。
児玉 もちろん、社外秘事項はお伝えしません。ただ、格好をつけてもしょうがないです。「こういう課題があります」と、包み隠さずにお伝えしていかないと、パートナー企業からも信用されない。そのような判断をしています。
良いところ、変えていくべきところをオープンにする。そこに共感いただき、ともに解決していこうというお話につなげるためにも、こちら側の課題は、差し支えない範囲でお伝えしています。
高橋 オープンにすることで、より多くの方々の叡智を集められることにつながる。
児玉 ご提案いただいた新規の製品・サービスが、先進的で素晴らしい取り組みであるときは、もっと多くの事業会社に知ってもらいたいと考えます。おそらく、他社さんも程度の差はあれど同じような課題をお持ちだと思うからです。
ですから、こちらから「国内初や業界初の事例を一緒に作りませんか」と、パートナー企業に対して必ず「逆提案」しています。そのための協力は惜しみません。
そして、製品・サービスの良い点、改善が必要な点も遠慮なくフィードバックさせていただく、という姿勢で臨んでいます。
高橋 どのようなフィードバックをされているのですか。
児玉 たとえば、パートナー企業の製品開発の方と当社社員が直接対話する場を設けることや、ユーザー会のような利用者主導のコミュニティの確立などを提案しています。
私が支援会社時代に担当したお客さまは、そのような顧客の声を積極的にいかす働きかけを、パートナー企業に対してつねにされていたのです。そうした振る舞いから、私自身も多くを学んできました。
対立を乗り越え、「客と業者」でなく本音を言い合える関係に
高橋 では実際に、パートナー企業とはどのような関係を築いているのでしょうか。

児玉 私が当社へ入社して、8年が経ちます。その間に進めてきたプロジェクトや施策を振り返って、画期的だったと思うものには、なんでも本音で語り合えるパートナー企業の存在という共通点があります。
しかし初めから、良好な関係が構築できていたわけではありません。「画期的である」ということは、それだけ推進するリスクも高いですから、お互い守りに入ってしまう場合もあります。
高橋 ビジネスですから、弱みや隙を見せてはいけないと考えてしまいますよね。では、どのようにして、お互いの守りの体制が変わっていったのでしょうか。
児玉 チームビルディングの考え方の1つに、タックマンモデルがあります。チームは模索、混乱や対立、認識の一致を経て、共通の目標に向かって成果を生み出すチームに成長するというものですが、そのようなプロセスをパートナー企業と共に、段階的に、そして意識的に踏むようにしていました。
高橋 事業会社とパートナー企業が同じ方向を見て、「現況を変えていこう」という想いがあるからこそ、進めるのだと感じます。

児玉 昨年当社では、70弱のプロジェクトを実施しました。そのなかでも、最もビジネスインパクトの大きかったプロジェクトでは、キックオフの段階から当社、開発パートナー両社の役員・責任者同士が、プロジェクト成功のために隠しごとなく、遠慮なく意見を言い合おうということを確認しました。
スケジュールもタイトであったことと、技術的なチャレンジが山積みだったからです。問題を先送りしない。現場で解決できなければ、役員・責任者同士で対話し、必ず答えを出す。お互いに至らない点があれば、指摘し合い改善する。契約を越えたある種の信頼関係です。その甲斐もあって、プロジェクトは成功裡に完遂できました。
ともすれば、事業会社のIT部門と支援企業は「客と業者」の関係になりがちです。事業会社内においても、業務部門とIT部門がそのような関係になってしまうことがあります。ITによる価値実現をしたいのは事業会社側ですから、「客と業者」の関係は丸投げを加速し、価値そのものを自ら棄損することになるのでよくないです。
そういう事業会社は減ってきているとは思いますが、事業会社とパートナー企業の対等な関係があってこそ、戦略的なイニシアティブやプロジェクトの真の成功を成し遂げられるのではないでしょうか。
お互いのプロ意識が刺激し合い、ベストプラクティスが生まれる環境
高橋 次に、視点を変えて、児玉さんが支援企業の立場から事業会社と関わっていらっしゃったときのお話を聞かせてください。当時、お客さまとはどのようなコミュニケーションを取られていましたか。
児玉 日本アイ・ビー・エムではITプロセスコンサルタントとして7年間、セールスフォース・ジャパンでは、カスタマーサクセスマネジャーとして最重要顧客向けのアドバイザリー、プログラムマネジメントに関わっていました。
基本的に、ITコンサルティング会社やツール提供会社は、既存のアセットを組み合わせたオファリング・ビジネス(※1)です。自分たちが持つ知見、製品やサービスで、お客さまの期待に応えようと考えがちなところがありますよね。
けれども、私が当時担当していたお客さまは、いずれも日本を代表する企業です。ITにおいても国内初、業界初の取り組みを多く手掛けられていますから、「他社でやっているのをそのまま持ってきて」という依頼は1つもありませんでした。むしろ、有り物のアセットをそのまま提案しても突き返されるわけです。
「どこも手掛けていないような仕組みや取り組みを」「現行の製品・サービスには存在しない新しい機能を」とご相談いただくのですが、その時点で自社ではお応えできないリクエストも多かったです。アセットやベストプラクティスをかき集めるか、なければ一から拵える(こしらえる)しかありませんでした。

児玉 もちろん、過度な作り込みや個社事情に対応することは、フィット・トゥ・スタンダード(※2)から離れ、技術的負債を生み出す可能性があります。しかし、お客さまが競争優位に立つためには、他社と同じことを同じタイミングでやっていたらだめなのですよね。
加えて、私が担当したお客さまは、決して自社ITの利害だけを考えてはいませんでした。自分たちの取り組みが、その製品・サービスの普及を後押し、同業や他業界の事業会社にも広がることも見据えていた。そういう矜持(きょうじ)をお持ちでした。そして成果につながるものであれば、苦言にも耳を傾ける謙虚さをお持ちでした。
そんな「プロ意識」の高さに溢れるお客さまに対し、私自身もプロフェッショナルとして結果で応えたいと感じるようになりました。多忙な日々でしたが、国内初、業界初の事例を創出し、少なからずお客さまの経営戦略の実現の一助になれたことは、プロフェッショナル冥利に尽きました。
またこのときのお客さまの振る舞いが、事業会社へ転職してからの自身の物事の考え方の基調になっています。本当に、お客さまに恵まれました。
「期待に応えられるか?」の不安より、「お客さまの成功に貢献したい」が勝る
高橋 営業をはじめとしたお客さまと接する担当にとって、「お客さまからどうやって信頼を得るか?」は課題です。児玉さんは、なぜご自身がお客さまから信頼されていたのだと思いますか。
児玉 信頼されていたかどうかは、当時のお客さまがご判断されることですが、私なりに大切にしてきたのは、プロフェッショナルとしてお客さまからの期待に応え続ける、ということでしょうか。
そして、そのお客さまのお役に立ちたい、と強く想い、行動していくことですね。後者は、相手側にもそう想わせる「器量」が必要です。私は先ほど申し上げたとおり、お客さまに恵まれていました。
私の仕事観を大きく変えた、ある保険会社さまを担当したときは、お客さまのことを理解したくて、IT部門だけでなく、さまざまなビジネス部門やグループ会社の方々と接し、お客さまの立場に近づこうと努力しました。また、その先のステークホルダーの立場も理解したくて、保険募集人になろうと思ったこともありました。募集人になることは叶いませんでしたが(笑)。

高橋 外の会社からお客さまを知ることは限界があると思います。しかし、児玉さんが、お客さまの立場に立って話を聞き、お客さまと同じ当事者として取り組んできたことが、信頼につながっていたのではないかと感じます。
一方で、営業の場面では自分たちのソリューションを思い浮かべながらお客さまの話を聞いてしまいがちです。「お客さまのご要望を、自社の技術力で実現できるだろうか」「自社でできないことまで求められてしまうのではないか」と、不安を抱くとも思うんです。
児玉 私の場合は、お客さまの期待に応えたい、成功に貢献したいという想いが、不安を上回っていたのかもしれません。
「自社のサービスを契約してほしい」ではなく、どうしたらお役に立てるのか。そのために自分の本職ではないことも積極的に引き受けていました。それが結果として、私自身の新たな専門領域を確立する契機になっています。
ITプロセスコンサルタントだった私が、後にソフトウェア、クラウドサービスに関わるようになれたのも、お客さまからのご相談がきっかけでした。私が新たな能力を獲得するときには、常にお客さまの存在がありました。お客さまに育てていただいて、今の私があります。
パートナー企業の力を引き出す企業は組織が成熟している
高橋 児玉さんが「お客さまのために」という想いを持たれる源泉は、どこにあるのでしょうか。
児玉 お客さまへの支援を通じて、社会のためになりたい、また同じような想いを持っているお客さまと共創したい「願望」かもしれません。
私の仕事観を変えた保険会社さまは、事業に対する責任感は大変強いものでしたし、時にはそれが厳しさとなってパートナー企業である私たちにも向けられました。しかし、その期待に応えたいという風土が自社だけでなく他のパートナー企業にありました。
営業からSE、PM、コンサルタントまで一体となって、どうしたらお客さまに価値をもっと出せるか、時には激しい議論を戦わせたこともあります。また、パートナー企業同士の壁を越えて、お客さまへの価値実現のために共創することもありました。
この経験を通じて、パートナー企業のケイパビリティを引き出せる事業会社の力が、非常に重要であることを知りました。今、事業会社にいる私自身も、そういう存在でありたいですね。
高橋 パートナー企業の力を引き出してくれる事業会社の特徴を知りたいです。
児玉 組織としての成熟度が高いことが挙げられますね。それは決して会社の歴史や規模だけで決まるものではなく、経営理念や普遍的な価値観が確立され、組織内に浸透している状態です。
そのときの経験もあり、現在当社も方針や施策をお伝えする前に、「生命保険会社として何を大切にしているか」ということを、理念とともお伝えするようにしています。
たとえば、当社は業界初の取り組みを実現することに、こだわりを持っています。これは決して、新しいものが好きだとか、他社に競争心を燃やしているからではありません。私どもは、誰よりもお客さまに寄り添い、お客さまのことを考える保険会社でありたい。
その結果として、他社を先駆した取り組みを実現する。そして、実現するのであれば良いものを、他社の方々にも参考にしていただけるようなことをやっていこうと考えています。

高橋 良い事例は、他社だけでなく他の業界にも波及しますよね。自分の仕事がその会社内にとどまらず、世界や未来を良くしていくことへつながっていくのだ、と感じました。
そして、会社と会社の関係とは、個人と個人の関係の重なりだと思うんです。たとえば、「会社の方針はこうだけど、個人としてはもっと先で、こんなことを描いている」という強いビジョンをお持ちのお客さまがいらっしゃいます。
私はそれを、表ゴールと裏ゴールと表現しますが、会社の建前としてのゴールだけでなく、相手の個人的な想いのゴールにも目を配りたいと考えています。その個人の想いを打ち明けてくださり、そこに共感できる関係性が理想だなと。
「これを達成することで良い世界が描けるんだ」と共有できた瞬間はすごく嬉しいですし、良い関係が作れると考えています。
共依存の関係から、対等なパートナーシップを育むためには
高橋 事業会社とパートナー企業、両方のご経験を持つ児玉さんは、両社が対等な関係であるために、どのような関わりが必要だと思われますか。
児玉 パートナー企業の変化や事情を理解したうえで、仕事をする意識が大切ではないでしょうか。
ソフトウェアハウスやSIer、コンサルティング会社も、人月の労働集約型ビジネスを維持しつつ、人に依存しないビジネスへの転換を図ろうとしています。
一方で、有償稼働率、いわゆる人月でビジネスをしている実情があります。優秀な外部人材を長期にわたって「確保」し続けるためには、事業会社側も価値ある仕事を彼らのために「創って」いかなければならない。そのようなパートナー企業のビジネス事情にも一定の配慮をすべきと私は考えます。
また、いつでも「別れられる」ようにパートナー企業とは適切な距離感を保つことも大切だと考えています。
高橋 「別れられる」とは、製品やサービスの契約が終わるということですね?
児玉 そうです。人間関係で捉えると、いつでも別れられる、というのは世知辛いことですが、製品やサービスについては、事業会社はロックインされないようにする。パートナー企業は設計・サービス思想に沿わない誤った使い方、過度なカスタマイズをさせないようにする。
その状況をつねに双方で確認しながら、変えるべきことがあれば躊躇なく変える。そうすることが双方にとって最も価値的であると考えています。それを実現するためにも、事業会社とパートナー企業双方が忌憚のない意見を言い合える、良い意味での緊張感と適切な距離感が必要、ということですね。
高橋 変化しなくてはならないのに、変えられない事業会社とパートナー企業の関係は、共依存的とも言えますね。
児玉 人や組織は、変わることよりも、それに抵抗することにエネルギーを投じる傾向がありますね。当社が、パートナーシップをつねにオープンにして、さまざまな企業からの提案を求めているのは、変わることへの抵抗を回避したいという想いの現れなのかもしれません。

つねに複数の選択肢を持ち、他者の気持ちを自分ごと化する
高橋 終わりに、正解がない時代、児玉さんが意識されていることを教えてください。
児玉 コロナ禍以降、強く意識するようになりましたが、どんなことに対してもつねに複数の選択肢を持つことですね。
歴史があり事例も多い金融業界のプロジェクトにおいても、事前に想定できないようなトラブルが以前よりも増えていて、プロジェクトそのものが頓挫してしまうケースがあります。当社においても対岸の火事ではない。ゆえに私は、リスク対策の一環として複数の選択肢を持つようにしています。
正解のない時代を進むなかで、ケガは避けられないとしても、直撃や大ケガは回避したい。私個人で何かを決めるときも、複数の選択肢を持つことを意識しています。
そして、身近な人だけでなく、普段接することのできない方々の気持ちになって共感し、自分ごと化することでしょうか。
高橋 共感から、この人に尽くしたい、貢献したいという思いが生まれるのかもしれません。1人の熱量に巻き込まれ、それが次第に伝播して組織として良くなっていく。ある意味で、属人的ですよね。
児玉 属人性は排除すべきという考え方は組織を運営する側の論理です。近年はむしろ属人化、ここに極まれりという状況が加速している。加えて生成AIの登場で「その人にしか出せない、その人ならではのバリュー」も問われ始めてもいます。
もちろん、特定の人物に依存した仕事は見直したほうが良いですが、1人ひとりが輝き、マーケットバリューを高めることはまったく悪いことではありません。「成果をあげるには貢献に焦点を合わせねばならない」と言ったのは、かのドラッカーですが、今こそこの言葉の真意を捉える時かもしれません。
私は新卒から25年、IT企業4 社、現職の生命保険会社まで一貫してITの領域で働いてきました。日本の事業会社におけるITは、諸外国に比べても外部依存性が高く、環境の変化に俊敏かつ柔軟に対応できなかったり、トランスフォーメーションが進みにくい土壌を生んでいます。そんな日本のITに、少しでも良い形で変化を起こせる1人でありたい、と思っています。

才流のコンサルタントが解説
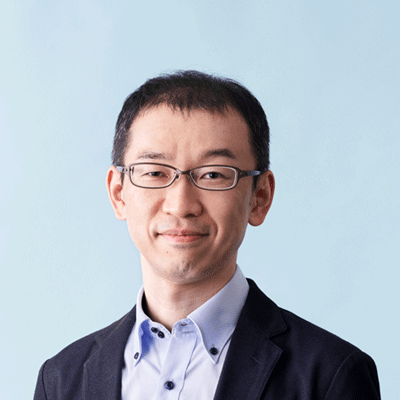
オリックス生命保険の児玉さんは、事業会社と支援企業の関係を、対等な立場で価値創造に取り組むパートナーシップへと進化させてきました。
このお話は、IT企業や開発会社だけでなく、あらゆる業界の企業が、パートナー企業との協働において応用できるものだと感じます。
児玉さんが指摘されるように、事業会社が支援企業の力を最大限に引き出すためには、両者が本音で語り合える信頼関係を築き、共通の目標に向かって価値創造に取り組むことが不可欠です。
そのためには、支援企業には高度な専門性やノウハウの提供が求められる一方で、事業会社には、パートナーを巻き込みながらも自立的に課題解決を推進できる人材の育成が求められます。
両社がそれぞれの強みを活かしながら、プロフェッショナルとして対峙し続けることの大切さに、改めて気づきました。
私自身も、次の打ち合わせでは、いつもよりお客さまの話に耳を傾けてみよう。寄り添ってみよう。そして、お客さまの成功にどう貢献できるか考えてみよう。と思うインタビューとなりました。
児玉さん、貴重なお話をありがとうございました!
(撮影:関口 達朗)
※1 オファリング・ビジネス:受託開発ではなく、自社の標準製品・サービスを提案し、ビジネス課題の解決を行うこと
※2 フィット・トゥ・スタンダード:ソフトウェア開発において、既存の標準やベストプラクティスに適合させること
