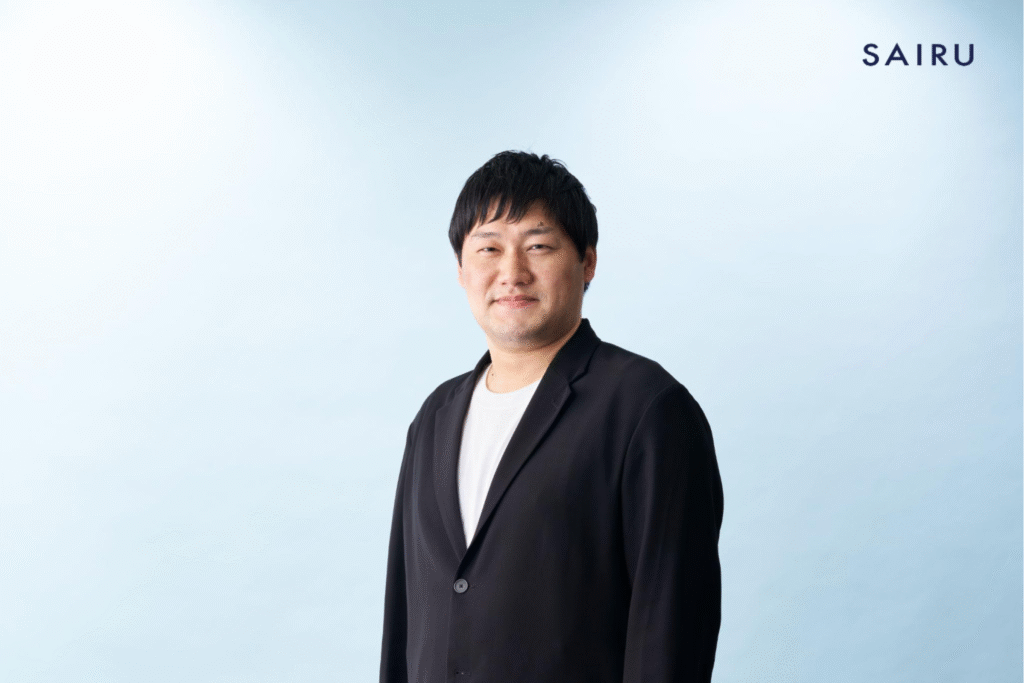
高野匠司
Takano Takuji- 職種
- シニアコンサルタント
「本当に解決すべき課題は、表面に見えている問題の奥深くに隠れている」——才流(サイル)で新規事業開発やBtoBマーケティングの支援に携わるコンサルタントの高野匠司(たかのたくじ)はそう語る。
新卒で入社したコンサルティングファーム時代に、50社以上の企業を支援した実績を持つ。その後転職したBtoBスタートアップでは、40名規模の組織マネジメントを経験。現場と経営の両輪を担いながら、会社の急成長フェーズを支えた。さらに、自らも起業を経験している。
現在は才流でお客さま企業の課題解決に挑んでいる高野に、これまでのキャリアや才流で働く魅力について話を聞いた。
コンサルティング現場で発見した「本質的な課題の見つけ方」
ーこれまでのキャリアで印象に残っていることを教えてください。
才流に入社するまで、コンサルティングファーム、事業会社、起業と経験を積んできました。
新卒で入社したコンサルティングファームでは、中小企業を中心に50社以上の企業支援に携わりました。マーケティング支援、新規事業開発、採用強化、事業責任者代行、事業再生といった幅広いテーマに取り組ませてもらいましたね。
企業支援の現場は、業界、商材、企業規模、地域性、さらには経営者の価値観までが複雑に絡み合っています。そんな中で、ある共通点に気づきました。それは、目に見える問題の背後にはしばしば別の要因が潜んでいるということです。
ーその共通点に気づいたきっかけは何でしたか。
事業再生の現場では、売上急落といった表面的な数字の問題に対して、データ分析や施策の議論だけでは改善につながりませんでした。真のボトルネックは、経営層が失敗続きで自信を失い、リスクを取って意思決定を進める力を失っていることでした。“意思決定の停滞”こそが本質的な課題だったのです。
こうした経験を重ねる中で、本質的な課題を見つけるための共通点が見えてきました。まず、症状として現れている問題と、根本的な課題は別物であること。次に、当事者ほどその業界の常識や組織の文化に縛られて、本質的な課題を見落としやすいこと。そして解決策は、実は複雑な戦略ではなく、業界や組織の「当たり前」を見直すことから始まるケースが多いことです。
このような複雑な状況を紐解いていく過程で、課題の構造を読み解く力を身につけることができました。
また事業再生のような困難な現場では、どんなに論理的に正しい施策でも、現場の人たちが納得して動いてくれなければ意味がありません。経営者や社員の方々と正面から向き合い、数字の裏にある”人の気持ち”を読み取りながら信頼関係を築く。その過程で、人に寄り添うことの重要性を学ばせてもらいました。

ーコンサルタントとして充実した経験を積むなかで、なぜ事業会社への転職を考えたのでしょうか。
29歳のとき、知識と経験の幅をもっと広げたいと考え、BtoB向けのITプラットフォームを提供するスタートアップに転職しました。
入社してすぐに、セールス、カスタマーサクセス、コールセンターなど複数部門にまたがる40名規模の組織マネジメントを任されました。マネージャーとして個々の能力を引き出して、組織として機能させることの難しさを実感しましたね。
同時に、経営メンバーとして会社全体の事業戦略にも深く関わりました。年度計画の設計や市場選定、新サービスの方向性など、経営的な意思決定を担いながら、現場の状況も把握する。いわば“現場と経営の両輪”を担う経験をさせてもらったんです。
当時の会社は、外部資金を受けて急成長を求められるフェーズ。月次で成果を出す短距離走と、将来を見据えた長距離走を同時に走るような環境でした。目の前の数字(ソロバン)と描きたい未来(ロマン)の両立は想像以上に大変でしたが、その葛藤を体感できたのは貴重な経験だったと思います。
才流を選んだ理由は、変化を恐れない柔軟性と相互尊重の文化
ー才流への転職の経緯を教えてください。
事業会社を退職した後、次のキャリアを模索していた時期がありました。そんなとき、才流で働いていた事業会社時代の同僚から「副業でいいから手伝ってほしい」と声をかけてもらったのが最初の接点でした。
才流のメンバーと仕事をして、競争的な雰囲気がまったくないことに驚きました。それぞれが自分の得意領域を持ち寄って、対等に議論しながらプロジェクトを前に進めていく。その空気感に、これまでにない心地よさを覚えました。
また、経験豊富なメンバーが多いものの、考えに固執せず変化を恐れない柔軟さがありました。必要があれば支援スタイルを柔軟に変えていくしなやかさに、「ここでなら、これまでの経験を活かしつつ、まだまだ成長できそう」と確信できました。
才流を選んだというより、自然とその文化に惹かれていましたね。お互いの強みを認め合う環境が、自分の強みを最も発揮できる場だと実感したのです。
ー現在、高野さんはどのようなプロジェクトを担当することが多いのでしょうか。
大手企業の案件を中心に取り組んでいます。複数部門との連携が必要で、慎重な意思決定プロセスがあり、扱うテーマも多面的で複雑な状況が多いです。そんな中で、各部門の最適解を全体最適にどうつなげ、合意形成しながら実行フェーズまで持っていくかが常に問われます。
興味深いのは、一見マーケティングの問題に見えても、実際には組織設計や意思決定の仕組みに本当の課題があるようなケースが多いこと。私がコンサルティングファーム時代に発見した“共通点”は、企業規模を問わず共通して見られる構造なのだと実感しています。
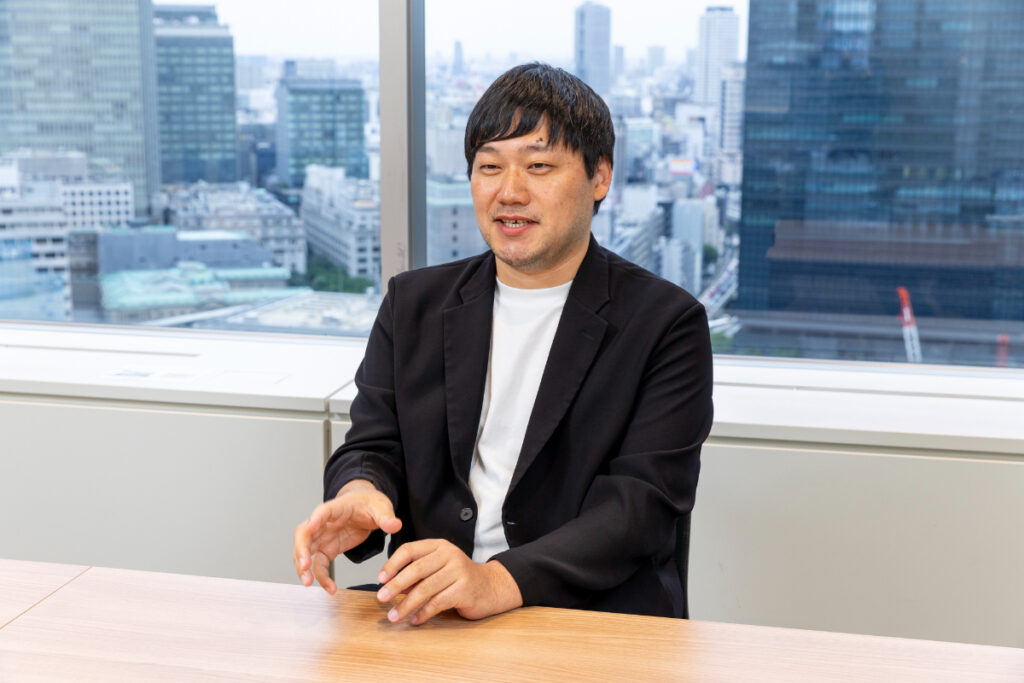
現場の葛藤を知るからこそ、実行可能な解を共につくれる
ーご自身の経験から、コンサルタントとしてどのような価値を提供できると考えていますか。
私の場合、支援する側と支援される側、両方の立場を経験していることが大きな強みです。事業会社での組織マネジメント経験を通じて、事業推進における現場の制約や人間関係のしがらみ、意思決定の難しさを身をもって知っているからこそ、机上の空論ではない現実的な支援を提供できます。
また、マネージャー経験もあるので、プロジェクトの各場面で担当者が直面する不安やプレッシャーはよくわかるんです。ですから、単に施策を提示するのではなく、担当者が一歩を踏み出せるように、心理的にも寄り添いながら並走したいと思っています。
さらに、大手企業ではジョブローテーションが多いため、担当者が変わっても後任者が迷わないよう、組織にノウハウを残すことを意識しています。
ー高野さんが思う、才流の提供するコンサルティングの競争優位性について教えてください。
コンサルティングファームの多くは設計やしくみ化に秀でていますよね。一方で、私たちは実行現場の混乱やプレッシャー、組織内の人の感情のような複雑なリアリティに対しても解像度高く向き合うのが得意です。お客さまに深く入り込んだ伴走支援ができるのも、私たち自身が同じような立場で悩み、実行してきた経験があるからこそです。
また、才流には蓄積されたメソッドがあるので、課題解決までの時間を大幅に短縮できることも大きな価値だと思っています。

知的好奇心とチーム力を両立するカルチャーが才流の魅力
ー才流の組織文化や働き方について、どのように感じていますか。
これまでのキャリアを振り返ると、才流の働き方は自分にとってちょうどいいバランスだと感じています。
コンサルティングファーム時代は、コンサルタント一人ひとりが自分の看板を背負い、成果を競い合っていました。汎用性の高い思考力とスキルは身につきましたが、ときには孤独や疲弊を感じることも。
事業会社は真逆で、チームで一点突破する協働型の組織でした。組織を動かす力や、仲間と成果を出す喜びを実感できましたが、もっと多様なテーマに取り組みたいという物足りなさもありましたね。
才流では、その両方のいいとこどりができています。プロジェクト単位では、コンサルティングファームのように業界やテーマが幅広く、知的好奇心を刺激されています。一方で、事業会社のようにチームで協働し、互いに補い合いながら進める文化もちゃんと根づいている。競争ではなく協働、分断ではなく共創の空気のなかで、自分の強みも、チームの力も最大化できている感覚があります。
ー今後の目標や展望について教えてください。
これまでのキャリアにおいて、立場は違えど一貫して組織の変革と成果創出に関わってきました。分断された課題をつなぎ、構造で捉え直す力が自分の武器になったと思っています。
今後もその武器を活かし、日本企業の競争力向上に貢献していきたいと考えています。特に、大手企業が抱えがちな構造的な課題に対し、現場に寄り添いながらお手伝いをしていきたいです。
個人的には、自分でユニークな事業を立ち上げることにも関心があります。昔から、少しヘンテコなものや人と違う切り口に惹かれる性格で。誰かに「その事業、おもしろいね」と言ってもらえるような、ちょっとニッチで尖った事業を手がけてみたいです。構造を捉える力と好奇心、この両輪を活かして、まだ誰もやっていない価値の提供にも挑戦していきたいと思っています。
ー最後に、才流に興味を持っている方にメッセージをお願いします。
才流は、経験豊富なメンバーが互いを尊重し合いながら、本当に良い仕事を追求できる環境だと思います。短期的な成果だけでなく、長期的な価値創出を大切にする文化があり、個人の成長と会社の成長が自然に両立できる場所です。
これまでの経験を活かしながらも新しい挑戦をしたい方、チームで連携しながら大きなインパクトを生み出したい方には、非常に魅力的な環境ではないでしょうか。ぜひ一度、お話しできればと思います。

(撮影:ヤマダヤスヒコ)
